入塾のご相談時に圧倒的に多いのが、「文章題が苦手」というご相談です。
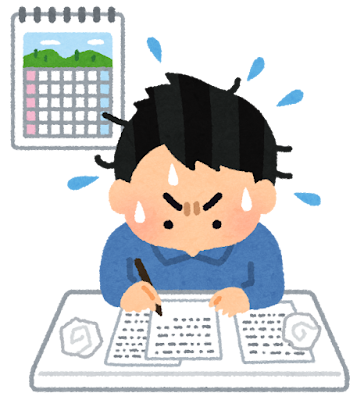
文章題と言っても様々ありますが、現在の学習指導要領では「考える力」を伸ばすため、どの科目も「長文化」される傾向にあります。
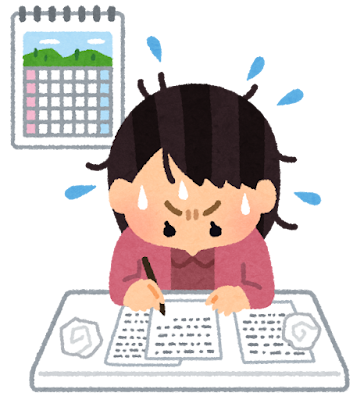
私が考える文章題対策は3つです。
①知っている語彙を増やす。
子供も大人も本を読まなくなったと言われて久しいですが、子供達に「ここ最近で教科書以外に読んだ本はある?」と聞くと、多くの子供達は「全然読んでいない。」と答えます。
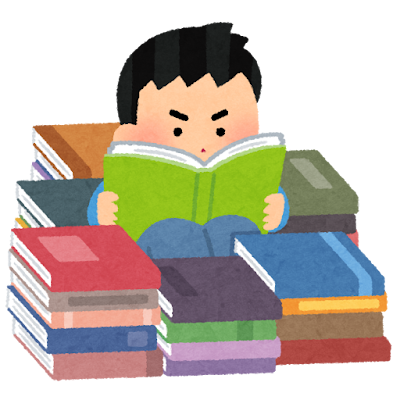
まれに図書委員の生徒さんや、本好きの生徒さんは、「◯◯を読んだ。」と回答してくれてうれしくなります。
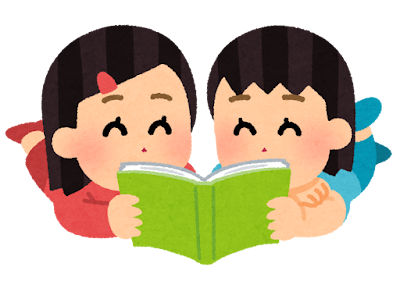
本を読んで身につくのが「語彙力(ごいりょく)」です。語彙とは「ある人やある国が持っている単語の総体」のことを指しますが、本を読むことで様々な語彙に触れます。わからない語彙があれば、国語辞書で調べましょう。
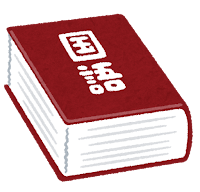
自分が知っている語彙が増えれば、難しい本も読めるようになるし、勉強でも問題が指図していることが理解出来る・想像出来るようになります。どんな本を読めば良いですか?と聞かれるケースも多いのですが、興味がある本であれば何でも良いと思います。
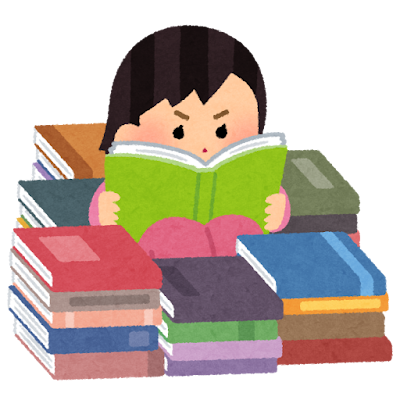
「あまりにも語彙が無くて、本を読んでいると間に合わない。」という方は、当ブログでも度々紹介する福嶋隆史先生の「ふくしま式 本当の国語力が身につく問題集」シリーズを学んでいくのが良いでしょう。語彙力教科の専用問題集です。中身を見てもらえば分かりますが、「確かに良く使う用語だけど、正確にはどういった意味があるのか?」そういった点をわかりやすく学ぶことが出来ます。

セルモの授業にも組み込むことが出来ます。語彙力に不安を感じる小中学生は、取組んで遅いということは無いので、今からでもやってみれば良いと思います。
https://www.selmo-machida.com/price/#course02
希望される方は、詳しくは下記ページをご覧頂き教室までご連絡をお願いします。
②文章の読み方を工夫する。
文章題を苦手にしている生徒さんに共通する課題として、「文章全体を何となく見て・読んで、分からない。」と判断する癖があります。

そこで思考が止まってしてしまい、それ以上考えが進まない・手が動かないわけです。
文章を読む時は文節で区切っていき、各文節ごとに「理解出来ている。」「理解出来てない。」と理解を分けることが大事です。

文節ごとに生徒さんにその意味を確認すると、意外と意味が理解出来ている場合もあります。
文節ごとに区切り、落ち着いて文章を読んでいきましょう。
③条件を紙に落とす、図式化する。
②と同様に、文章題が苦手な生徒さんは「頭の中で問題の解き方を考えてしまう。」癖があります。脳の中に一時的においておける情報量は大したことがありません。

まずは、文節ごとに区切って読んだ内容を、図や表にしてみる、数字が書いていればその条件を紙に書いてみる、そういった工夫をすることで、脳の中にあまり情報はおかないようにしましょう。

その図式化の仕方が分からなければ、学校や塾の先生に聞いて下さい。当然ながら学校や塾の先生は図式化することに慣れています。
次は、類題で自分でもそれを真似してみることです。真似するところから初めて、自分のものにしていきましょう。
絶対駄目なのは、学校や塾の先生に聞いて、うなずくだけで終わることです。自分でやってみないと意味がありません。
①から③にあげた工夫や取り組み以外にも色々対策はありますが、まずは取り組みやすいのが上記の内容です。

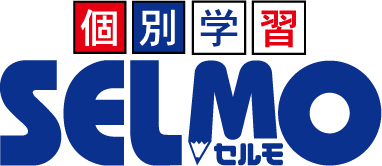



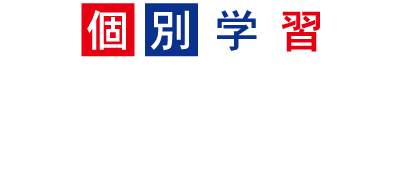 トップページへ戻る
トップページへ戻る