天気が良く過ごしやすい日曜日です。
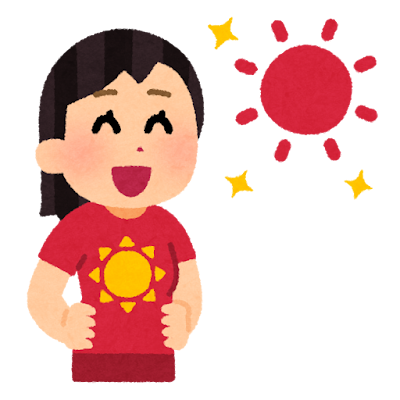
各教室では、1学期中間テスト対策授業を行っています。
成果を出すには、とにかくコツコツ一歩ずつです。
例えば数学は、計算問題では解き方をいかに忠実に守るかが大事です。
自己流でなんとなく解いたら、精度が下がります。
文章問題は、言葉の読解ができるかどうかがポイントです。言葉の意味を正確に把握し、「何を求める問題なのか?」自分の中で明確にしましょう。

ここに書いた事象を実現するには、ゆっくりで良いので「丁寧」「繰り返し」学習することが重要です。

苦手な人は、「急ぐ」「繰り返さない」癖があります。
スポーツを始めとして「習得するという行為」はすべて同じですよね。丁寧に繰り返す。
生徒さんには「ゆっくりで良いよ。丁寧にいこう。」と声がけします。
「コツコツ丁寧」を繰り返せば、自然とスピードは上がります。
そうは言っても、「勉強の苦手」から脱出出来ない人がいます。
それはなぜなのか?
GW中に読んだ本にヒントがありました。
「自己否定感」に関する本を読みました。

「自己否定感」とは、「私は間違っている、出来ない、苦手・・・。」という負の考え方です。

負の考えが重なると元気を無くします。負の考えはループすることが多く、なかなか脱出することが難しいです。

しかし、現実には多くの人が「自己否定感」を少なからず持っている。では、全員が「自己否定感」で苦しんでいるかというとそうではありません。それは何故なのか・・。
それは「自己否定感」にも2つあり、「克服型」と「逃避型」に分かれるからだそうです。
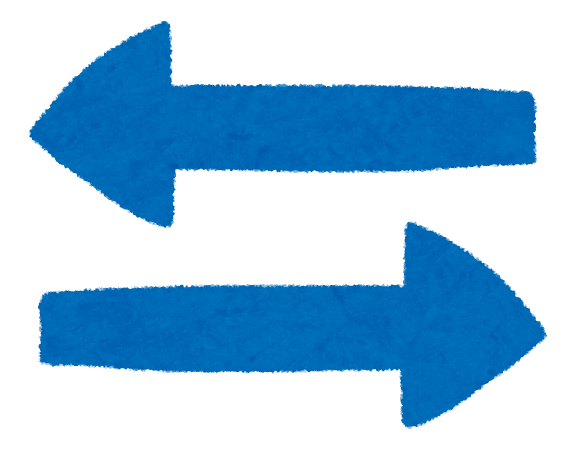
「克服型」は、誰しもが持つ「自己否定感」で感じた考えを「戦いのエネルギー」に昇華できるタイプの人です。

いわゆる「悔しい・できるようになりたい」ということですよね。
だから、自分の苦手や弱点と正面から向き合い、改善に向けて努力します。その積み重ねが、「成功体験・生きる喜び」に繋がります。いわゆる自己肯定感への「転換」です。
自己肯定感への転換を積み重ねた人は、ポジティブに生きていくことが出来るので「社会的成功」に繋がります。

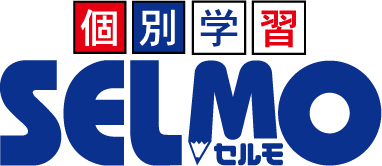



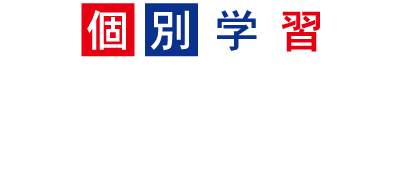 トップページへ戻る
トップページへ戻る


