いよいよ残す所、あと2回になった日帰り合宿勉強会です。

さて、レポートの前に、都立一般入試分割前期の倍率が発表されました。
都立分割前期倍率 [教室長:松本]
https://www.selmo-machida.com/wpsys/blog/12160.html

詳しくは松本のBlogをご覧頂きたいですが、生徒さん達には、
①取り下げ、再申請があるので最終倍率では無いこと。油断しない。
②取り下げ、再申請自体はなんら恥ずかしいことでなく、受験戦略の一つであること。
③倍率が高い学校を受験する生徒さんは、自身の現状の実力を冷静に分析して欲しいこと。
※過去問の得点や、模擬試験の状況を加味して分析して欲しい。
以上のことをお伝えしました。
例えば、偏差値50の学校を受ける場合は、過去問で安定的に平均点以上を取っている必要があります。

数学・英語・理科は60-65点、国語は75点、社会は55点がこの場合の最低得点となります。
もちろんベースとして内申点がありますので、内申点にリスクがある場合は上記の得点では合格出来ない場合もあります。
いずれにせよ、都立一般入試の生徒さんは明日9日(日)に冷静に親子でお話し頂き、最終的な意思を確認して下さい。
[社会歴史解説:平安時代]
◯前回の時点で江戸時代の解説に入っていますが、平安時代の解説が浅かったのでしっかりやっておこうと思い、時間を割きました。 
平安時代に限った話ではないですが、人物名や地名を暗記する歴史問題は都立ではほとんど出題されません。例えば、政治や武士の規律についての時代ごとの遷移など、総合的な知識が必要です。

昨日の平安時代の解説でも、十七条の憲法(飛鳥時代)→大宝律令:飛鳥時代から平安時代は格式へ変わっていったことをお話しました。要は、時代の変化・進化に合わせて法律も進化していったわけです。
武士をまつわる法律でも、御成敗式目(鎌倉時代)→建武式目(室町時代)→分国法(室町・戦国時代)→武家諸法度(江戸時代)と遷移していったことを覚えましょう。
なお、このあたりは次回の第10回で時代・律令・戦国法などの確認テストを用意しておこうと思います。
[理科解説:電力・電子・磁界]
◯前回の電圧・電流に続き、電力・電子・磁界などの公式、ルールを再確認しました。

難易度の高い範囲ですね。また、この電気分野に興味関心が無い生徒さんは、今まで学習を避けてきた傾向が強い範囲です。
丁寧に一つずつ基礎要素を解説しました。
ただ、この範囲も解説を聞いているうちは「そうだった、学校の授業で習ったことを思い出した…。」となりますが、実際に問題演習を重ねないと解けない単元です
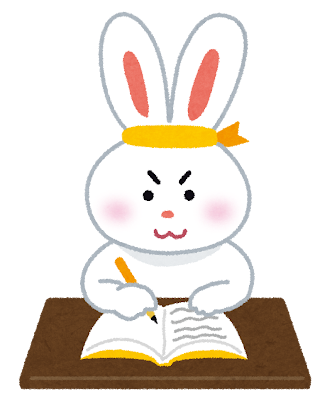
問題演習をきちんと重ねているかどうかは、生徒さんにより大きな差があります。
次回の最終回では、回路図の問題を中心に確認演習を実施したいと思います。
もちろん自宅でもきちんと取り組んで下さい。
[社会大問2・3演習、解説]
◯累計4回目、5回目の演習と解説を実施しました。

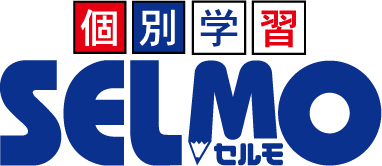



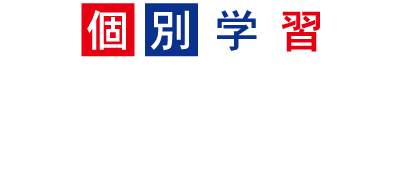 トップページへ戻る
トップページへ戻る