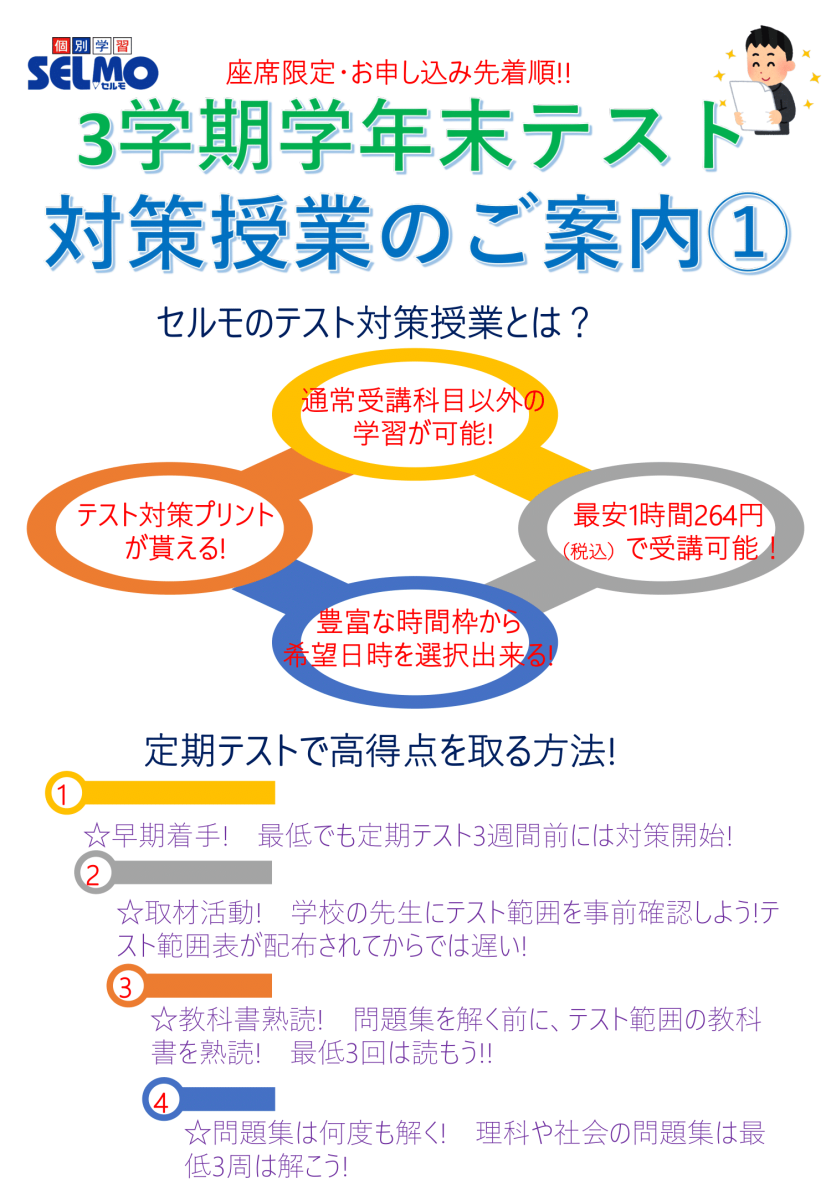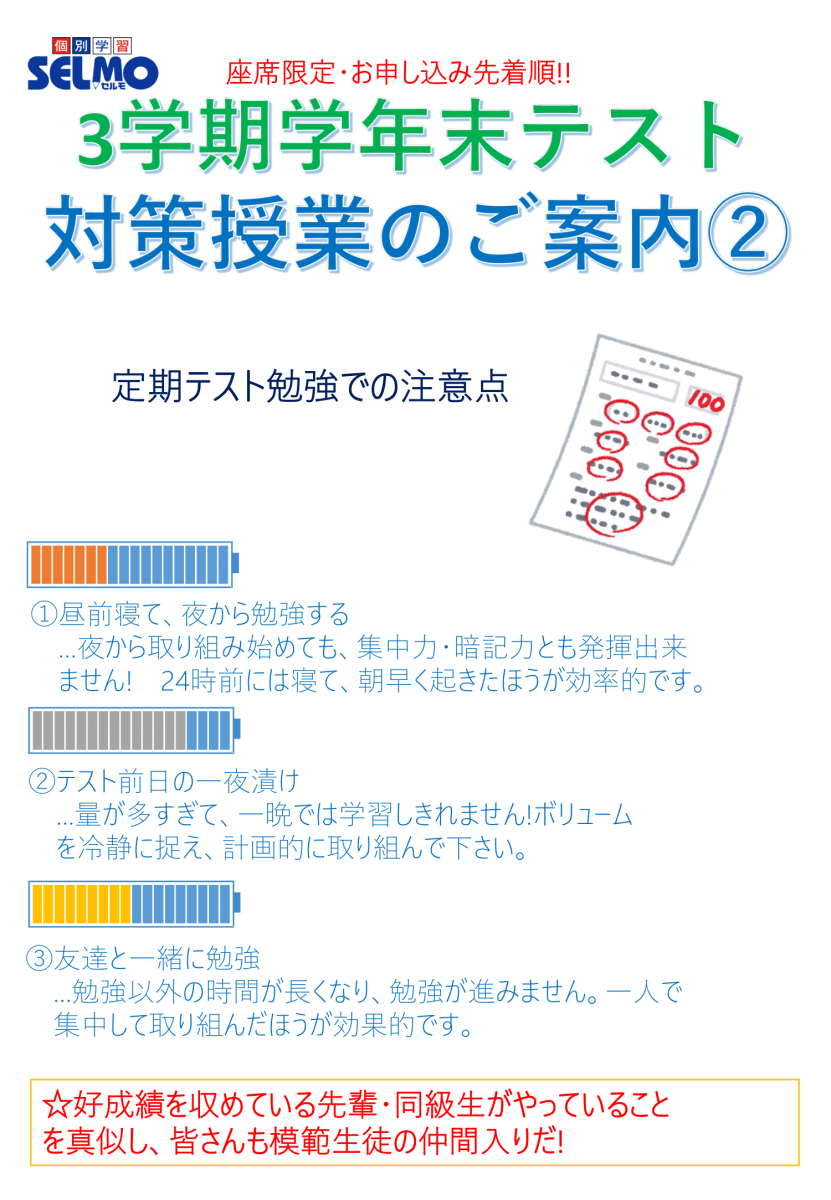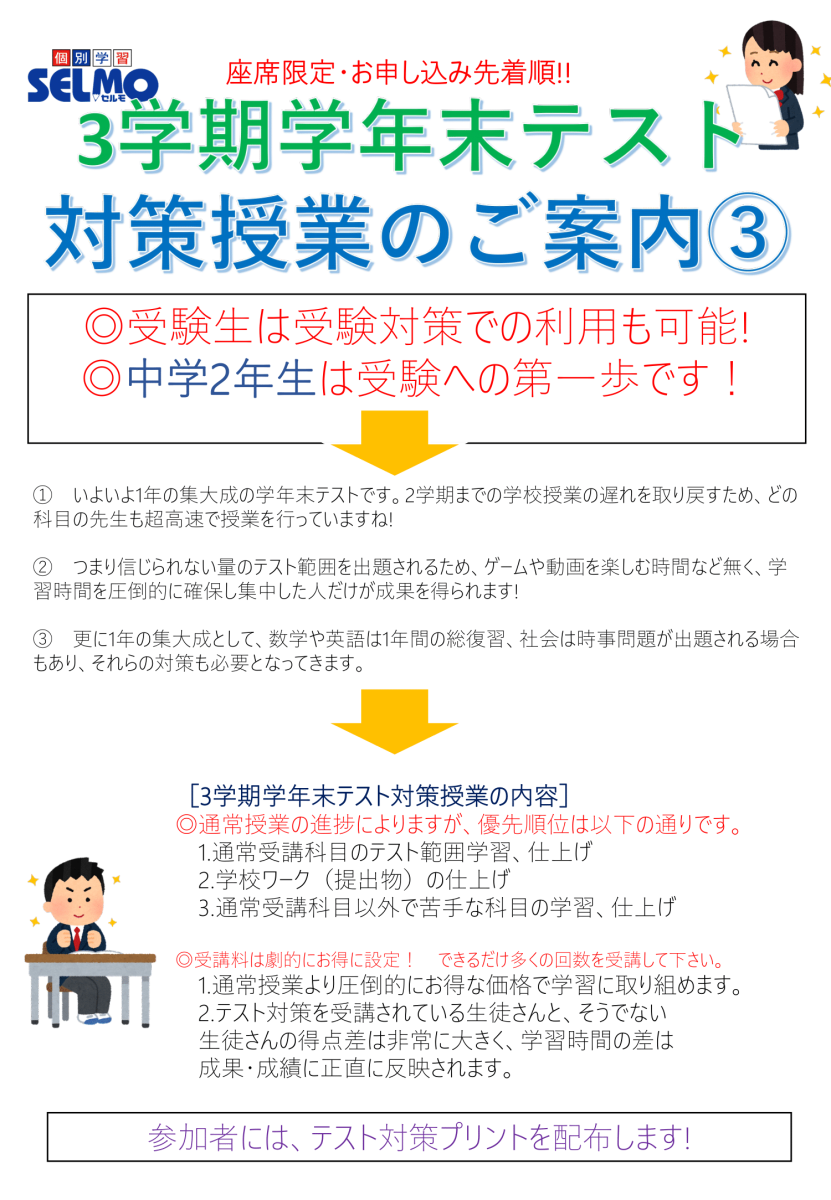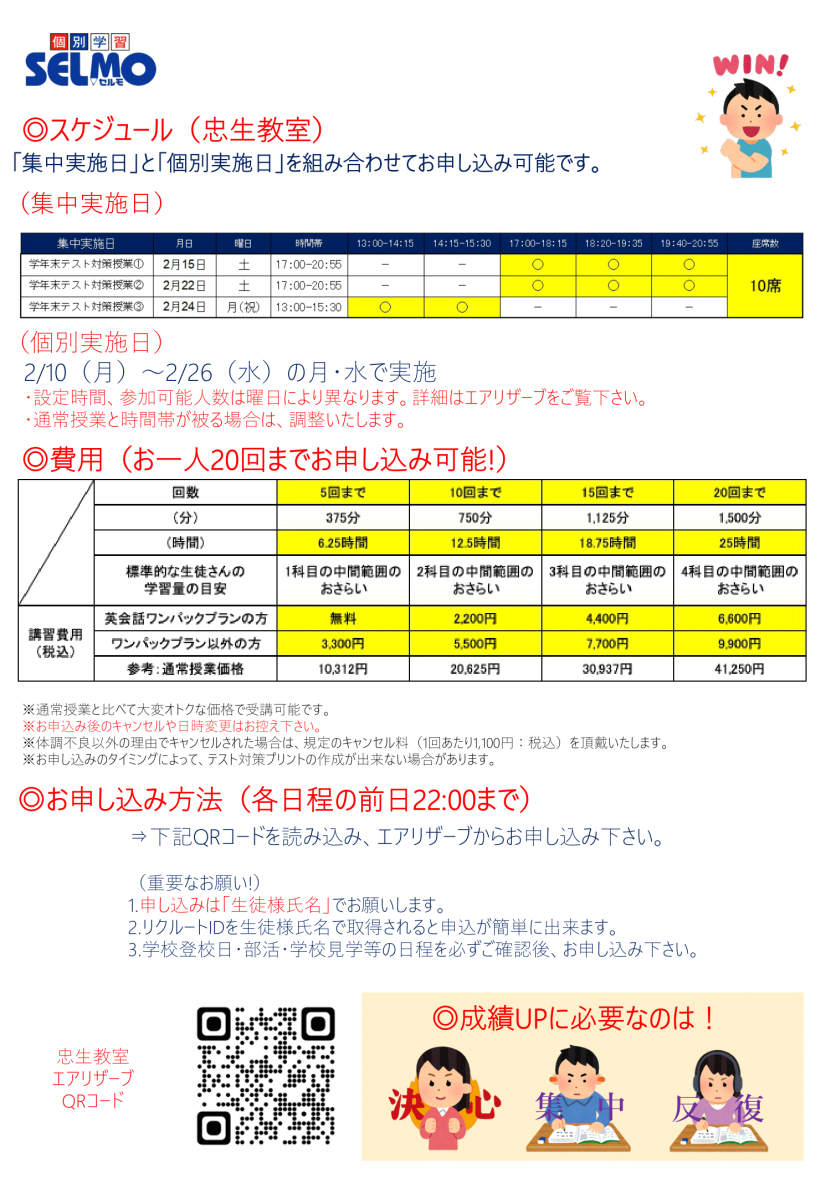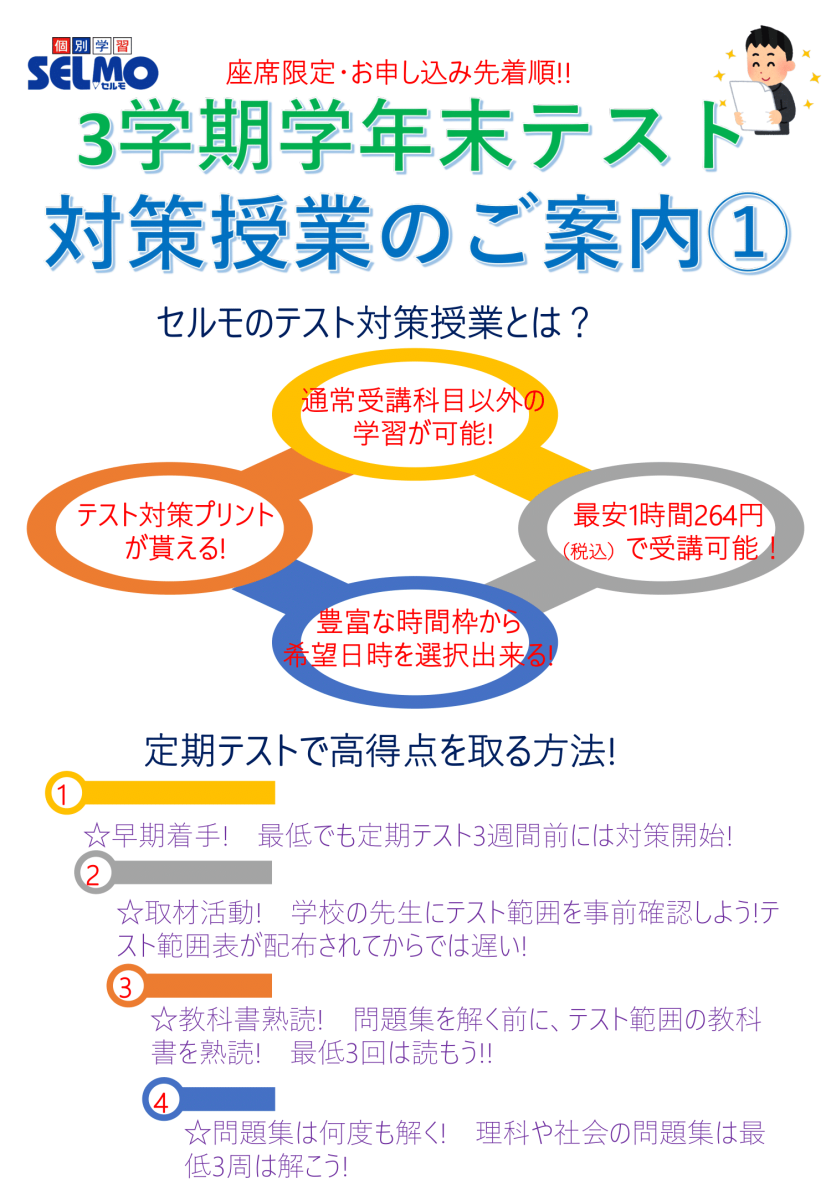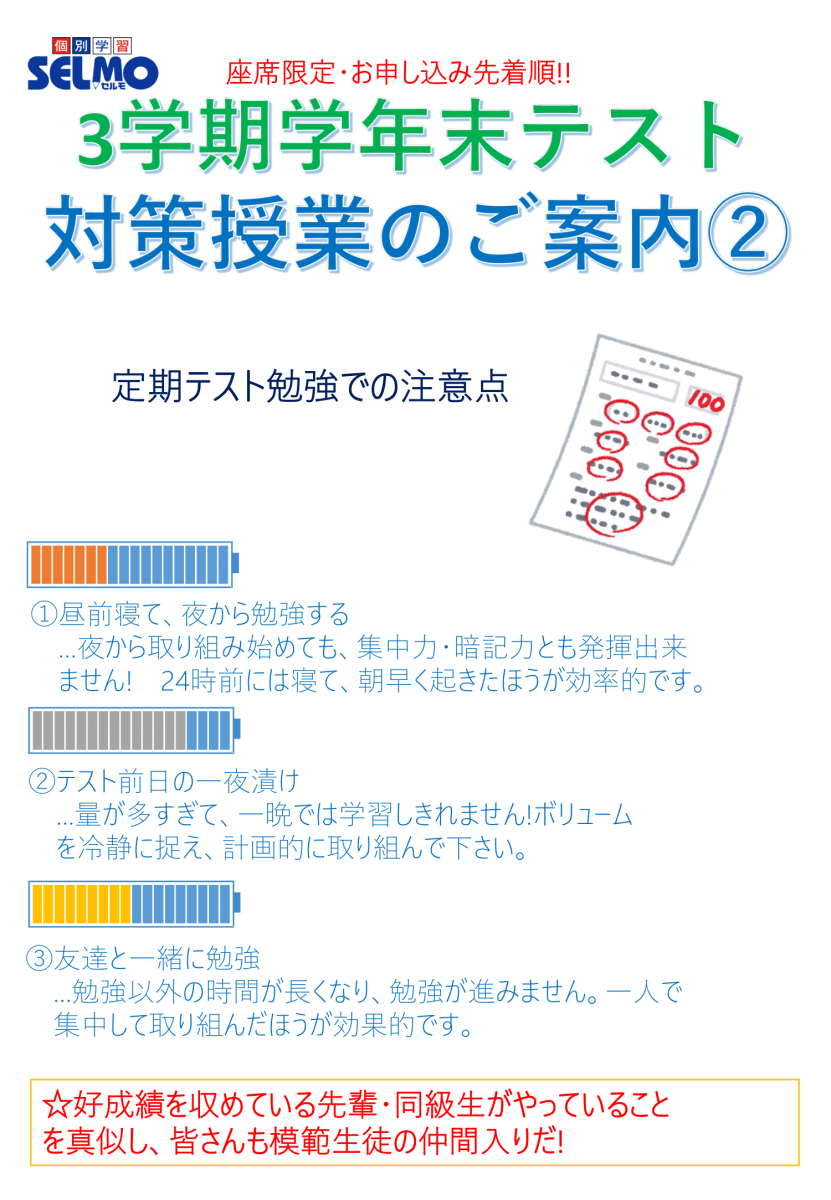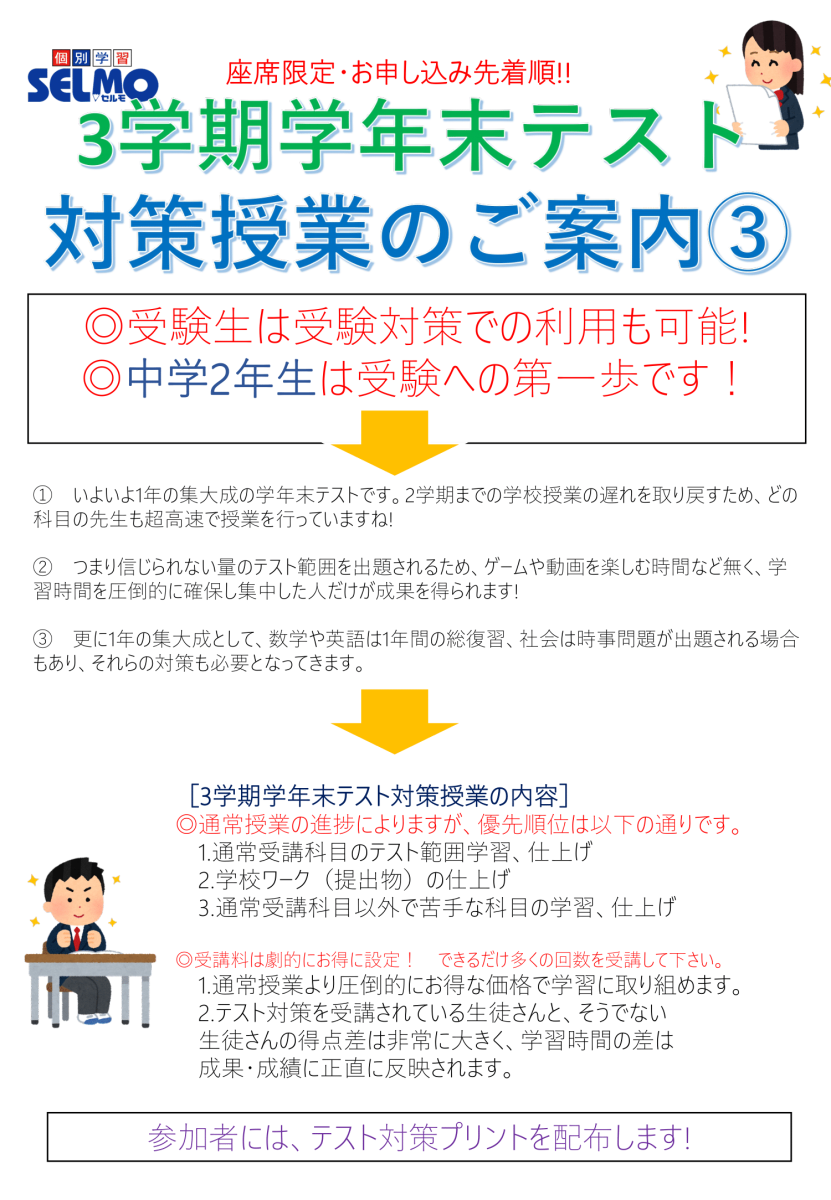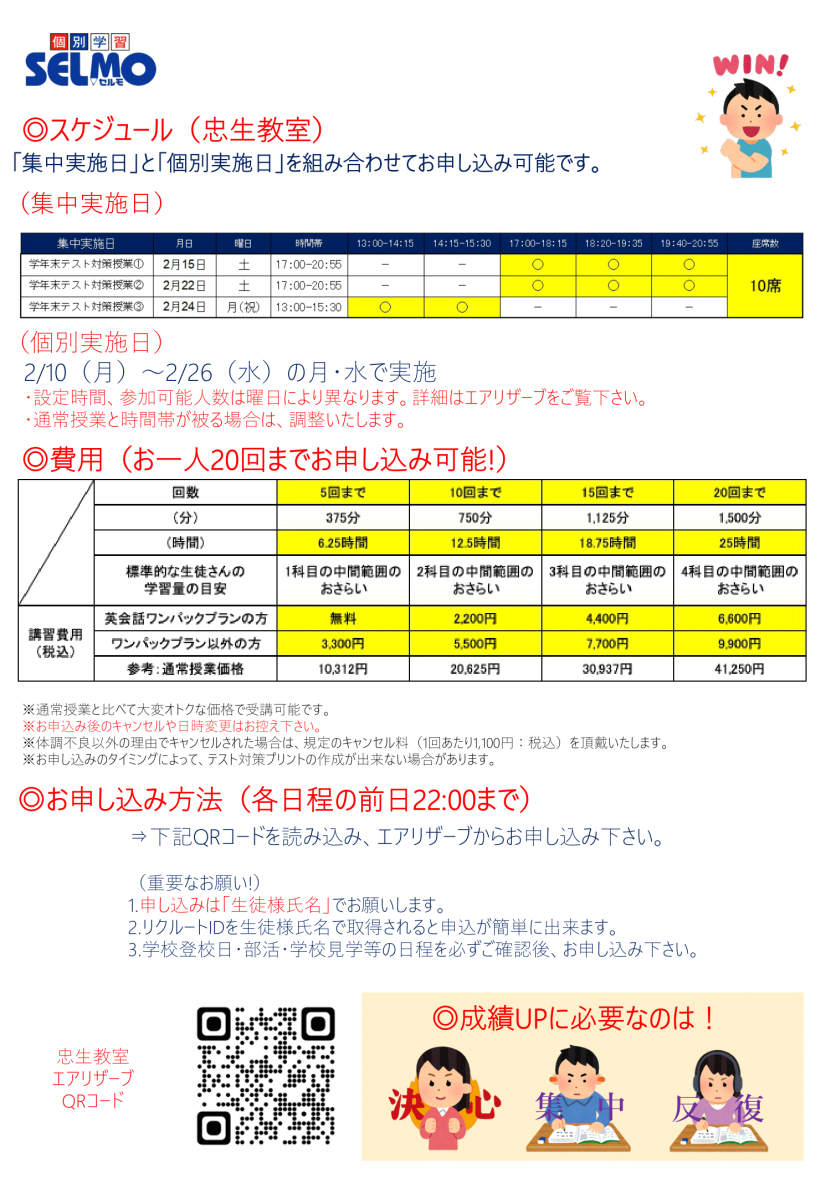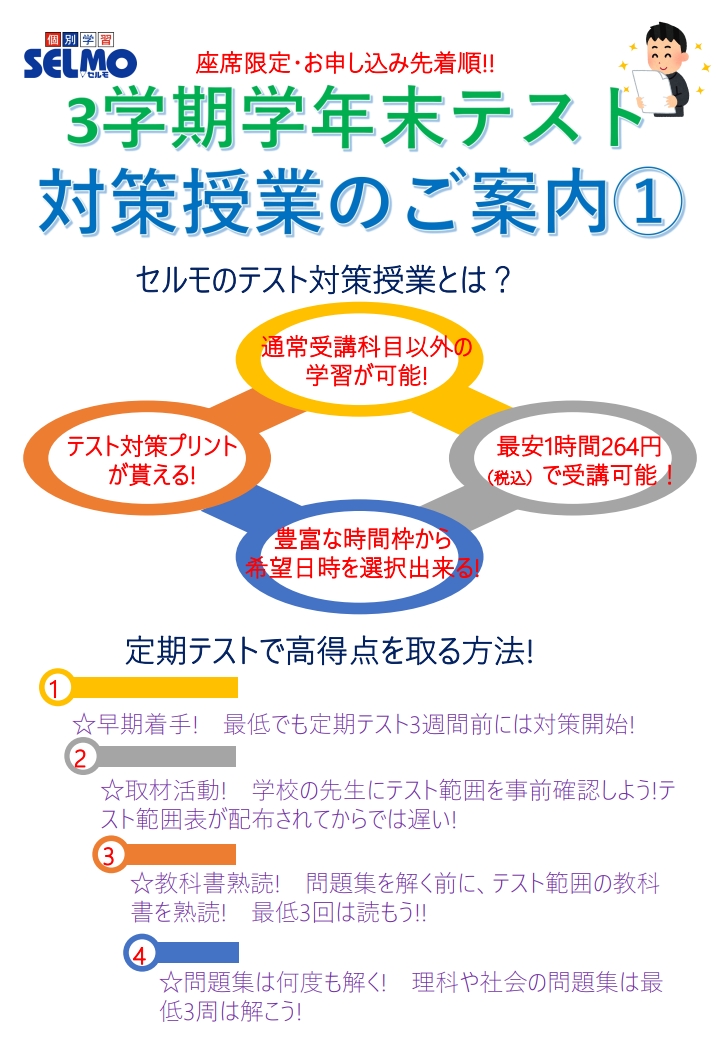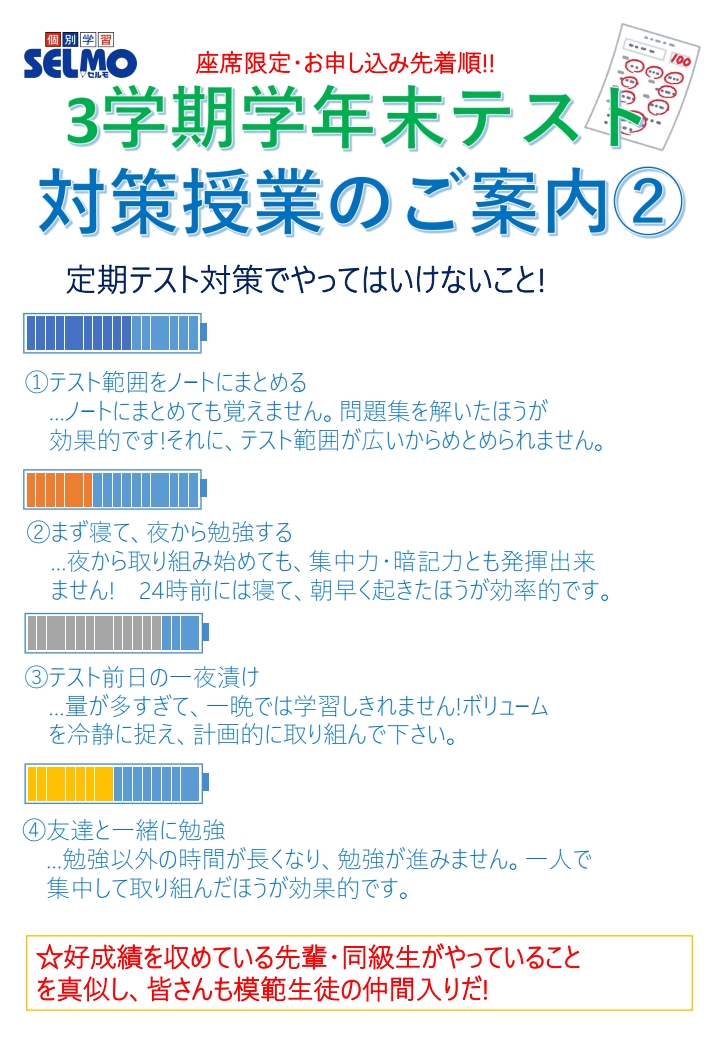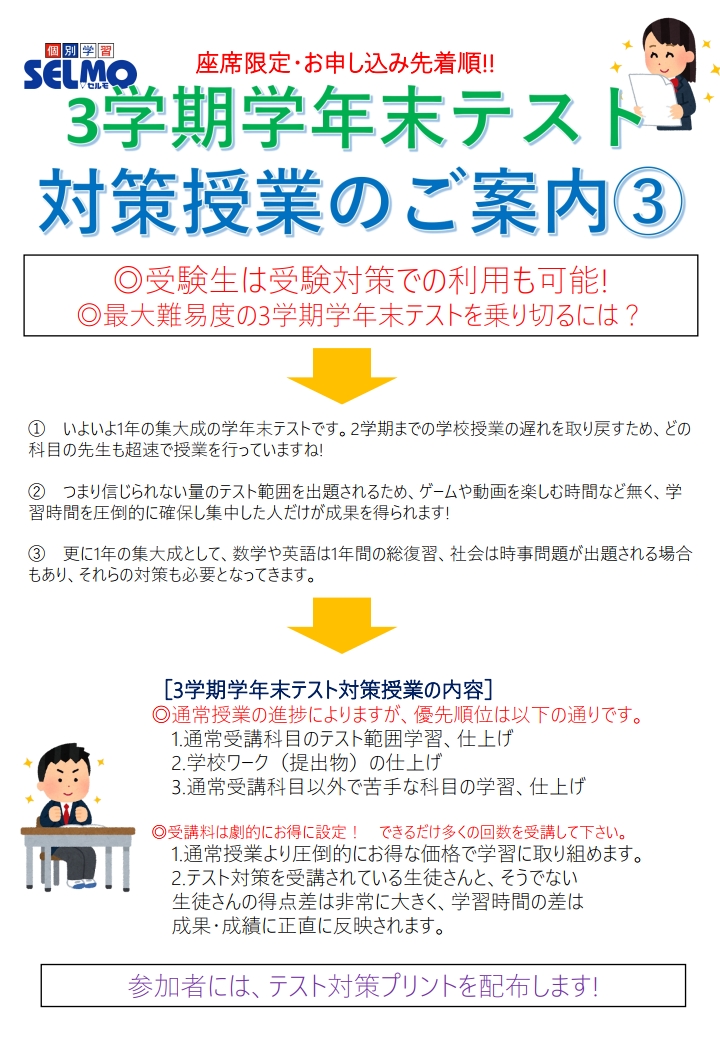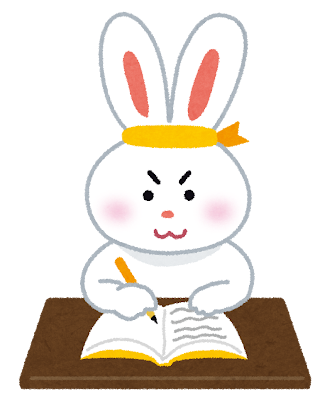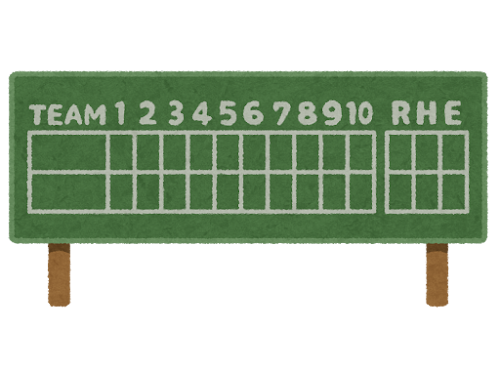様々な情報を定期的に
配信しております!
キャンペーンやイベントなどの情報から受験速報、
セルモ忠生教室からのお知らせなど更新させて頂いております。
気になる情報等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
いよいよ残す所、あと2回になった日帰り合宿勉強会です。

さて、レポートの前に、都立一般入試分割前期の倍率が発表されました。
都立分割前期倍率 [教室長:松本]

詳しくは松本のBlogをご覧頂きたいですが、生徒さん達には、
①取り下げ、再申請があるので最終倍率では無いこと。油断しない。
②取り下げ、再申請自体はなんら恥ずかしいことでなく、受験戦略の一つであること。
③倍率が高い学校を受験する生徒さんは、自身の現状の実力を冷静に分析して欲しいこと。
※過去問の得点や、模擬試験の状況を加味して分析して欲しい。
以上のことをお伝えしました。
例えば、偏差値50の学校を受ける場合は、過去問で安定的に平均点以上を取っている必要があります。

数学・英語・理科は60-65点、国語は75点、社会は55点がこの場合の最低得点となります。
もちろんベースとして内申点がありますので、内申点にリスクがある場合は上記の得点では合格出来ない場合もあります。
いずれにせよ、都立一般入試の生徒さんは明日9日(日)に冷静に親子でお話し頂き、最終的な意思を確認して下さい。
[社会歴史解説:平安時代]
◯前回の時点で江戸時代の解説に入っていますが、平安時代の解説が浅かったのでしっかりやっておこうと思い、時間を割きました。 
平安時代に限った話ではないですが、人物名や地名を暗記する歴史問題は都立ではほとんど出題されません。例えば、政治や武士の規律についての時代ごとの遷移など、総合的な知識が必要です。

昨日の平安時代の解説でも、十七条の憲法(飛鳥時代)→大宝律令:飛鳥時代から平安時代は格式へ変わっていったことをお話しました。要は、時代の変化・進化に合わせて法律も進化していったわけです。
武士をまつわる法律でも、御成敗式目(鎌倉時代)→建武式目(室町時代)→分国法(室町・戦国時代)→武家諸法度(江戸時代)と遷移していったことを覚えましょう。
なお、このあたりは次回の第10回で時代・律令・戦国法などの確認テストを用意しておこうと思います。
[理科解説:電力・電子・磁界]
◯前回の電圧・電流に続き、電力・電子・磁界などの公式、ルールを再確認しました。

難易度の高い範囲ですね。また、この電気分野に興味関心が無い生徒さんは、今まで学習を避けてきた傾向が強い範囲です。
丁寧に一つずつ基礎要素を解説しました。
ただ、この範囲も解説を聞いているうちは「そうだった、学校の授業で習ったことを思い出した…。」となりますが、実際に問題演習を重ねないと解けない単元です
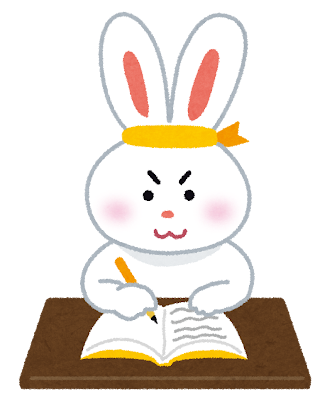
問題演習をきちんと重ねているかどうかは、生徒さんにより大きな差があります。
次回の最終回では、回路図の問題を中心に確認演習を実施したいと思います。
もちろん自宅でもきちんと取り組んで下さい。
[社会大問2・3演習、解説]
◯累計4回目、5回目の演習と解説を実施しました。

地理の総合問題が大問2・3ですが、だいぶん点数を取れるようになってきた生徒さんと、そうでない生徒さんにくっきり別れています。
点数が取れている生徒さんは、合宿の欠席が無く問題集をきちんと解いている、自身でも過去問題を解いている生徒さんです。説明中のメモもしっかり細かく取っていますね。
つまり、当たり前なのですが、知識・経験を積み重ね、解法のコツを掴んでいくしかないのです。
現時点で点数が取れていない生徒さんには、教科書の読み込みについてアドバイスをしました。世界と日本の各エリアの気候・産業・農業・漁業・生活様式など、改めて教科書を読み直し内容を確認しましょう。
なお、推薦入試合格組の生徒さんの中にも、きちんと解けていない生徒さんが複数いましたので、高校入学に向けきちんと復習しておきましょう。
[英語大問3演習、解説]
◯前回、時間の都合で実施出来なかった英語大問演習ですが、ギリギリなんとか実施出来ました。
累計5回目となりますが、こちらも社会同様に得点がしっかり取れてきた生徒さんと、そうでない生徒さんに別れました。
今回実施した令和2年度の大問3は比較的難易度が低い年度でした。
そういう意味からも、しっかり得点が取れなかった生徒さんは「解答の選択を今一度冷静に判断」する必要があります。
下線部の具体的な中身を問う問題が大問3のほとんどの問題です。正答は、下線部の前後に記載されているので、下線部の前後をしっかり読み込めが答えが正確に決定出来るはずです。
大問2,3でどれだけ得点が取れるかが勝負になるので、落ち着いて対処していきましょう。
なお、大問4について、出来れば次回2年度分は実施したいですね。
[まとめ]
◯毎年感じることですが、10回の日帰り合宿勉強会、本当に時間が足りません…。公立高校、特に都立高校を受験するための対策はとてつもない時間が掛かるのです。塾仲間の教室では、10回では足りずに15回・20回と回数を増やされているところも出てきました。
しかし、コストと時間の関係で、なかなかそこまでは難しいところ(指導側の労働時間に限界)もあります。それだけに、自身でもきちんと学習時間を確保することが重要です。敵となるスマホや動画・SNSの対策がキーでしょう。
新中学3年生の生徒さんは、高校入試説明会を来週以降実施しますが、このあたりのお話もしていきたいと思います。
受験生の皆さんは、試験前最後の日曜日無駄にしないよう過ごして下さい。10日、11日に私立併願入試がある生徒さんは、当日確実に実力を発揮して下さい。がんばって下さい!
強い寒波の到来とともに、都立分割前期試験の倍率が出ました。
まだ志願変更前ですので、多少の変動はあるかと思いますが、現時点での倍率です。
【昨年の倍率との比較】
令和6年度→令和7年度
〇 町田高等学校 1.42倍→1.12倍
〇 狛江高等学校 1.61倍→1.85倍
〇 成瀬高等学校 1.13倍→1.48倍
〇 松が谷高等学校
・普通科 1.36倍→1.38倍
・外国語コース 1.45倍→0.95倍
〇 小川高等学校 1.24倍→1.15倍
〇 片倉高等学校 1.22倍→1.23倍
〇 山崎高等学校 1.12倍→0.61倍
〇 永山高等学校 1.28倍→0.90倍
〇 野津田高等学校 0.61倍→0.51倍
〇 町田工科高等学校 1.05倍→1.05倍
〇 町田総合高等学校 1.03倍→0.97倍
〇 若葉総合高等学校 1.25倍→1.04倍
〇 工芸高等学校 1.44倍→1.52倍
山崎高校、永山高校と小川高校はもう少し倍率上がる気がします。
成瀬高校と松が谷高校から小川高校に志願変更される方が一定数いると予想されます。
高倍率の高校を受ける生徒たちは、当然ですがナーバスになります。
逆に倍率が1.00倍をきった生徒たちは、気持ちにゆるみが生じます。
それは普通のことです。
彼らに私から伝えたいこと。
まず、1.00倍をきった高校を受ける生徒は油断しないこと。油断したら負けです。
高倍率の高校を受ける生徒たちへ
どんなに高倍率でも、そこを突破できると思って進路指導してきました。
不安なら勉強してください。
例えば社会。キーワードを整理して体系化してください。
「法」
十七条の憲法、班田収授法、墾田永年私財法、御成敗式目、分国法、武家諸法度、公家諸法度、慶安の御触書、五箇条のご誓文、プロイセン憲法、大日本帝国憲法、ワイマール憲法、治安維持法、普通選挙法、国家総動員法、日本国憲法、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法
[権]
世界人権宣言、国際人権規約、平等権、自由権、社会権(生存権)、環境権、参政権、労働三権(団体行動権、団体交渉権、団結権)
[教]
仏教(タイ)、キリスト教(ヨーロッパ・アメリカ・オーストラリア)、イスラム教(西アジア及びマレーシア・インドネシア)、ヒンドゥー教(インド)、儒教、真言宗、天台宗、浄土宗、浄土真宗、朱子学、陽明学
まだまだ[乱][改革][主義][政治][戦争][気候][山や川][産業]など、まとめられることは山ほどあります。
国際河川と言えば、ドイツ・オランダを流れるライン川一択です。石油はほぼイスラム圏です。米はタイ、バナナはフィリピン、ピーマンは宮崎、レタスは長野、眼鏡は福井。夏に降水量が少ないのが地中海性気候、西岸海洋性気候は降水量が一定。
きりがありません。
理科であれば、苦手な単元に着手してください。
動物の体、地震、水溶液、回路図、イオン、天体など。
何も考えられないならば、漢字練習帳を開いて練習してください。
長かった受験勉強も去年の春期講習に始まり、夏期講習、日帰り合宿勉強会、冬期講習を経て、あと残り3週間です!
大丈夫、力をつけてきました。
誇りを持って、1日1日を過ごしてください。

いま各教室の受験生は、過去問題演習を重ねています。

生徒さんにより作戦は異なりますが、

①科目を絞って経験を積み重ねる。
②受験科目を順番に。
この2パターンで実施しています。
とある中学3年生です。偏差値45の学校を目指しています。
最新の令和6年度の数学から、過去に遡って実施していきました。

最初は40点を切る状態でしたが、6-7年経験を重ねることで60点台半ばまで来ました。
大問1の46点を満点取れるようになってきたことが大きいです。その他の大問1も(1)は正解出来るようになりました。
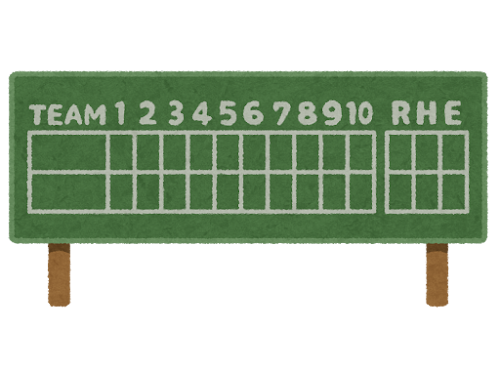
生徒も、最初は基礎計算で間違えたり、他の大問で得点が取れなかったりでがっかりしていたのですが、少しずつ手応えを感じてきたようです。
数学の平均点は年度によりブレはありますが60-65点です。

おおよそ偏差値50の学校を受けられる実力が付いたことになります。
ただし、受験問題というのは年度ごとに難易度の波があるので、安定的に65点取れるようにしていかなければなりません。
※偏差値55の学校であれば、70-75点必要です。
また、当然ながら数学がそういった状況になっただけで、他の科目も同じ状況に持っていく必要があります。
今は理科を同じ状況にすべく頑張っています。数学と同じ年数を重ねていますが、まだ手応えを得る領域までいっていません。

ただ、都立過去問題はあまり過去にもさかのぼれない(教科書の内容が変わっている)ので、他府県の同レベルの問題にも取り組んでいくなど、対策もバリエーションが必要です。
あと2週間ですが、受験生は学年末テスト対策授業で過去問演習を実施できますので、積極的に参加して下さい。