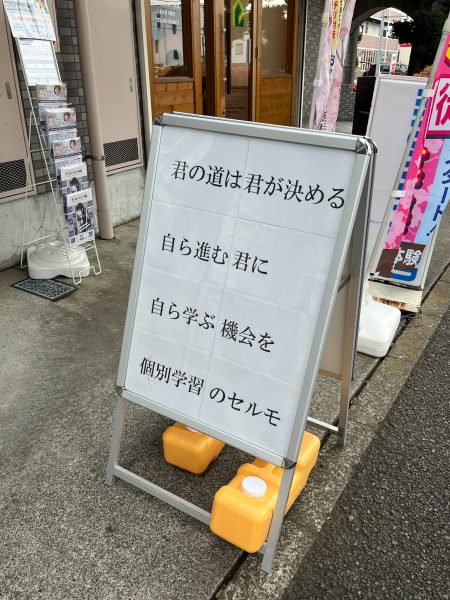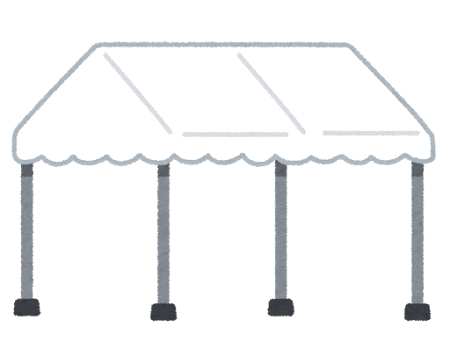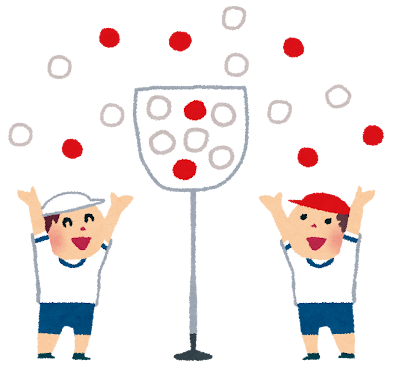高校部の生徒達と会話すると、「自転車での学校までの登校が大変!」という声をいくつか聞きました。

町田市内は坂が多いので、電動自転車といえどもなかなか大変です。

特に、周辺の都立高校だと松が谷・永山・成瀬・小川高校あたりに行く生徒さんは、大きな坂を登りきらないといけない生徒さんが多く、大変との声を過去から聞きます。
私立でも日大三高の最後の坂はなかなかのものです(笑)大妻多摩も大変なかなかのものです。

みんな「学校に到着する前に疲れてしまう。」とのことです。
電動自転車には何種類かあるのですが、少し値段は上がりますが、出来れば5段変速以上の電動自転車を買いたいところです。

3段変速だと、1段では軽すぎて大変で、2段だと重たい…という状況になります。
3段変速の電動自転車は、町田市内にもたくさんあるレンタル自転車のHELLO CYCLINGで試し乗りすることが可能です。

もし進学先の高校に電動自転車で通う場合は、色々なタイプを試してみると良いと思います。
なお、変速の段数以外にも、バッテリーの持ちも重要です。
坂でバッテリーを消耗するので、パワーモードで何キロ走るかチェックしておく必要があります。

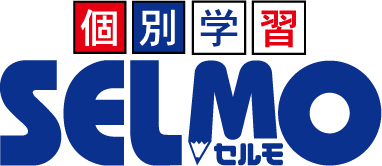



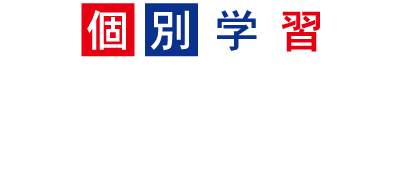 トップページへ戻る
トップページへ戻る